





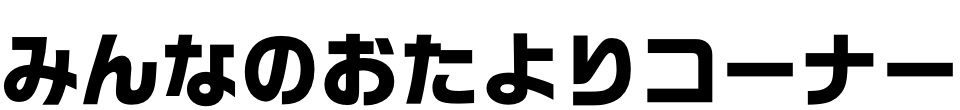

ぼくはタコのおさし身やたこ焼(や)きが好(す)きなので、このポスターをしっかり読みました。足が切れてもまた生えてくるのがびっくりしたし、ちょっとこわいなぁとも思いました。今度またタコを食べるとき、少しちがう味がするかもしれないです。
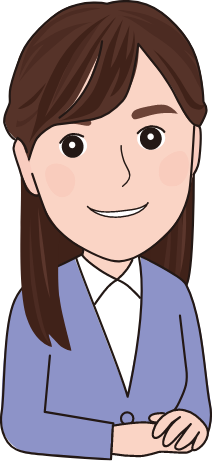
タコのおさし身や、たこ焼(や)きっておいしいよね!タコの生態(せいたい)にも興味(きょうみ)を持って、壁新聞(かべしんぶん)をしっかり読んでくれてありがとう!タコの足[うでと呼(よ)ばれる部分]が新しく生えるのはびっくりだよね。敵(てき)におそわれて、うでがちぎれてしまっても、だいたい数週間から数ヶ月かけて元通りになると言われているよ。ときどき新しくのびたうでが、と中で分かれてY字型(がた)になることもあるんだって。タコって不思議(ふしぎ)だね。
タコのお腹(なか)はないと思っていたけど予想外のところにあってびっくりしました。オスとメスのちがいが分からなかったけどこれを読んで初(はじ)めて知りました。
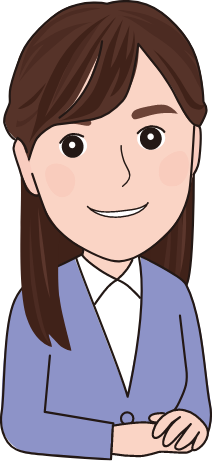
タコのお腹(なか)の中には、私(わたし)たちと同じように胃(い)、腸(ちょう)、じん臓(ぞう)のほか、メスには卵巣(らんそう)などが入っているよ。特(とく)ちょう的(てき)なのは「スミぶくろ」をもっていること。このスミぶくろでスミがつくられ、いざというときのために、たくわえているよ。敵(てき)に追われてにげるときにスミをはき出すことがあるけれど、スミで黒いモヤモヤをつくり、敵の目の前を見えにくくするんだ。イカもスミをはき出すけれど、イカと比(くら)べてタコのスミはサラサラで水に溶(と)けやすいんだ。だから水の中で黒い幕(まく)のように広がるんだよ。
タコのはきだすところを口だと思っていたけど読んでみたらろうとと呼(よ)ぶことが分かった。分かりやすいのでこれからも読みたい。
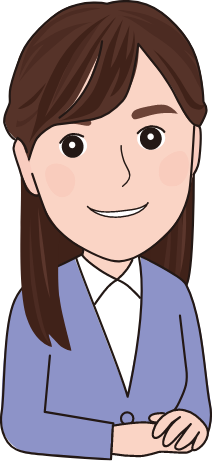
これからも読みたいと言ってくれてうれしいな。みんなに楽しんで読んでもらえる記事をつくるので、ぜひ楽しみにしていてね。タコがろうとから水をはき出すのは「泳ぐとき」だよ。ろうとから海水を吸(す)いこみ、その海水を勢(いきお)いよくはき出すことで、タコは前に進んだり、後ろに進んだりするんだ。ろうとの向きを変(か)えると、さまざまな方向に泳ぐこともできるよ。これはイカも同じだよ。
オスメスの見わけ方などが分かったし、世界一大きいタコや、世界一小さいタコがいることがわかりました。世界には、300種類(しゅるい)以上(いじょう)いることを初(はじ)めて知りました。ぼくの好(す)きなタコはコウモリダコです。
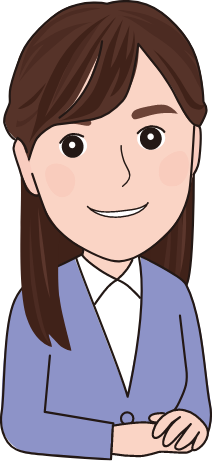
コウモリダコが好(す)きなんだね!コウモリダコは8本のうでがマントのような膜(まく)でつながっていて、特(とく)ちょう的(てき)な見た目をしているよね。その姿(すがた)がコウモリがさのように見えるから名付(なづ)けられたともいわれているよ。それにしても、タコにはいろいろな種類(しゅるい)、大きさがあるね。世界一小さいタコは、壁新聞(かべしんぶん)でしょうかいしたピグミーオクトパスのほかにも、ムラサキダコのオスや、ヘアリーオクトパスなどがいて、10円玉くらいのサイズだよ。世界一大きいタコのミズダコは、なんとギネス世界記録(きろく)にも認定(にんてい)されているんだって。
ぼくはタコのおさし身や、おすしが大好(だいす)きです。毒(どく)をもっているタコもいると知って、おどろきました。
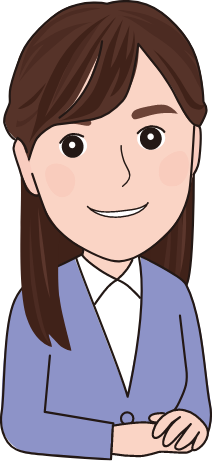
タコ料理(りょうり)をよく食べるのかな?実は、世界で最(もっと)もタコを多く食べている国は日本だよ。日本人はタコ料理になじみがあるけれど、世界の国の大多数はタコを食べる習慣(しゅうかん)がないんだって。世界全体のタコ消費量(しょうひりょう)の60%ほどを日本がしめていると言われているよ。タコには、体のつかれを和(やわ)らげたり、かん臓(ぞう)の力を高めたりしてくれる「タウリン」という栄養素(えいようそ)がたくさんふくまれているんだ。タウリンはカキやサザエなどの貝類(かいるい)や、イカにもふくまれているよ。
