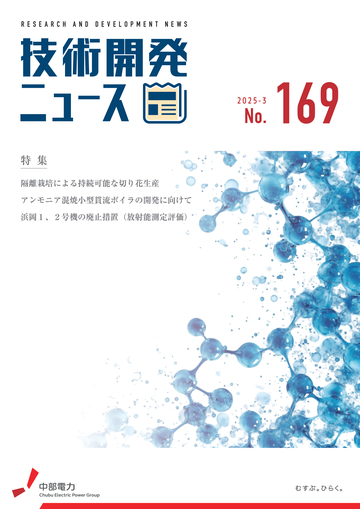技術開発ニュース No.169

- ページ: 67
-
研 究 紹 介
Introductions of Research Activities
加熱手法・条件の最適化
Optimization of heating methods and heating conditions
デジタル技術の活用により、加熱装置開発期間の短縮を目指す
執筆者
加熱装置の設計プロセスでは、担当者の知見・経験、過去事例、暗黙知をもとに複数の
設計パラメータを検討し、解析や実験・評価を行い、望ましい結果が出るまで評価・再検
討を繰り返し行っている。3D 解析技術の活用、プロセス改善と AI の組み合わせによるフ
ロントローディングにより技術開発スピードとレベルの向上を図る。
先端技術応用研究所
先端技術ソリューショングループ
薮崎 良介
1
②ヒータ配置、③ヒータ間隔
背景と目的
加熱装置の設計プロセスでは、設計者の知見・経験、過
去事例、暗黙知をもとに複数の設計パラメータを検討し、
解析や実験・試作評価を行い、望ましい結果が出るまで設
ヒータ、反射板
○被加熱物情報
・被加熱物サイズ:
350×350×20 [mm]
・被加熱物材質:鉄
④ヒータ長さ
⑤ヒータ出力
⑥ヒータ本数
○要求仕様
・加熱時間:300 [秒]
・目標温度:180 [℃]
・温度ムラ:±20 [℃]
①ヒータと平板の距離
被加熱物
第 1 図 平板の加熱実測評価環境
計パラメータ検討から試作評価を繰り返し行っている。そ
のため、設計者の経験値や発想力などの個人差により品質
が保てないことや手戻りの発生等が課題である。
そこで、当社はデジタル技術を活用し、加熱装置開発に
【モデル上面視】
おける最適な設計パラメータを提案し、最小限の実験・試
・解析結果
・解析エリア
Point5
Point4
作評価回数で開発期間の短縮および設計者の違いによらな
い標準化を実現するため、加熱手法・条件の最適化の取り
Point2
Point3
組みを行った。
2
熱流体解析
最適計算
加熱条件の最適化事例紹介
一例として加熱熱源として赤外線ヒータを用いた鉄系平
板の均一加熱装置の設計プロセスを紹介する。この場合、
加熱装置の設計パラメータは①ヒータと平板の距離、②
Point1
・設計パラメータ変更
・温度誤差最小/均一
第 2 図 3D モデル化、ソフトウェア連成
(a)設計パラメータ①:
温度が不均一で良くないデザイン
温度ムラ:-42~+27℃ ≧±20℃
(b)設計パラメータ②:
温度が均一で良いデザイン
温度ムラ:-11~+20℃≦±20℃
ヒータの配置、③ヒータの間隔、④ヒータの長さ、⑤ヒー
タの出力、⑥ヒータの本数等がある。これらパラメータを
ヒータ、反射板
検討し、第 1 図に示すような実測評価の環境構築を行い、
実測評価にてお客さまの要求仕様を満たす設計パラメータ
被加熱物
を検証した。
第 3 図 最適化計算結果
また、デジタル技術を活用して、第 2 図に示すように
実測評価環境を熱流体解析ソフトウェアにてモデル化を
行い、最適計算ソフトウェアにて設計パラメータを変更
し、解析デザインを生成させ、被加熱物表面の Point1 か
ら Point5 の 5 ヶ所に対して目標温度との誤差が最小かつ均
今後の取り組みと目指す姿
一となる最適化フローを構築した。この 2 種のソフトウェ
鋳造金型のような凹凸のある複雑形状をした被加熱物や
アの連成による最適化計算は、最適化アルゴリズムにより
誘導加熱等の他熱源への適用を検討し、3D 解析技術の活
自動実行されるため担当者リソースの有効利用が可能であ
用/開発プロセス改善と AI の組み合わせにより、フロン
る。本事例では、解析期間 7 日間を有し、第 3 図に示すよ
トローディングによる技術開発スピードとレベルの向上を
うに様々な設計パラメータの計算を実行し、温度ムラが小
図る。
さく均一な加熱が可能な設計パラメータの導出ができた。
この結果は、実測値と整合することを確認している。
67
3
技術開発ニュース 2025.03/No.169
�
- ▲TOP