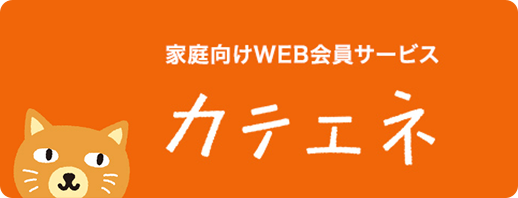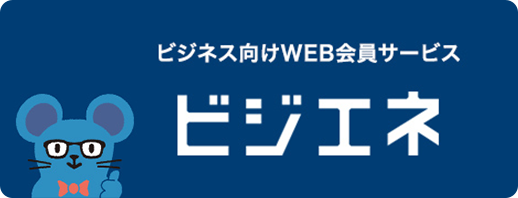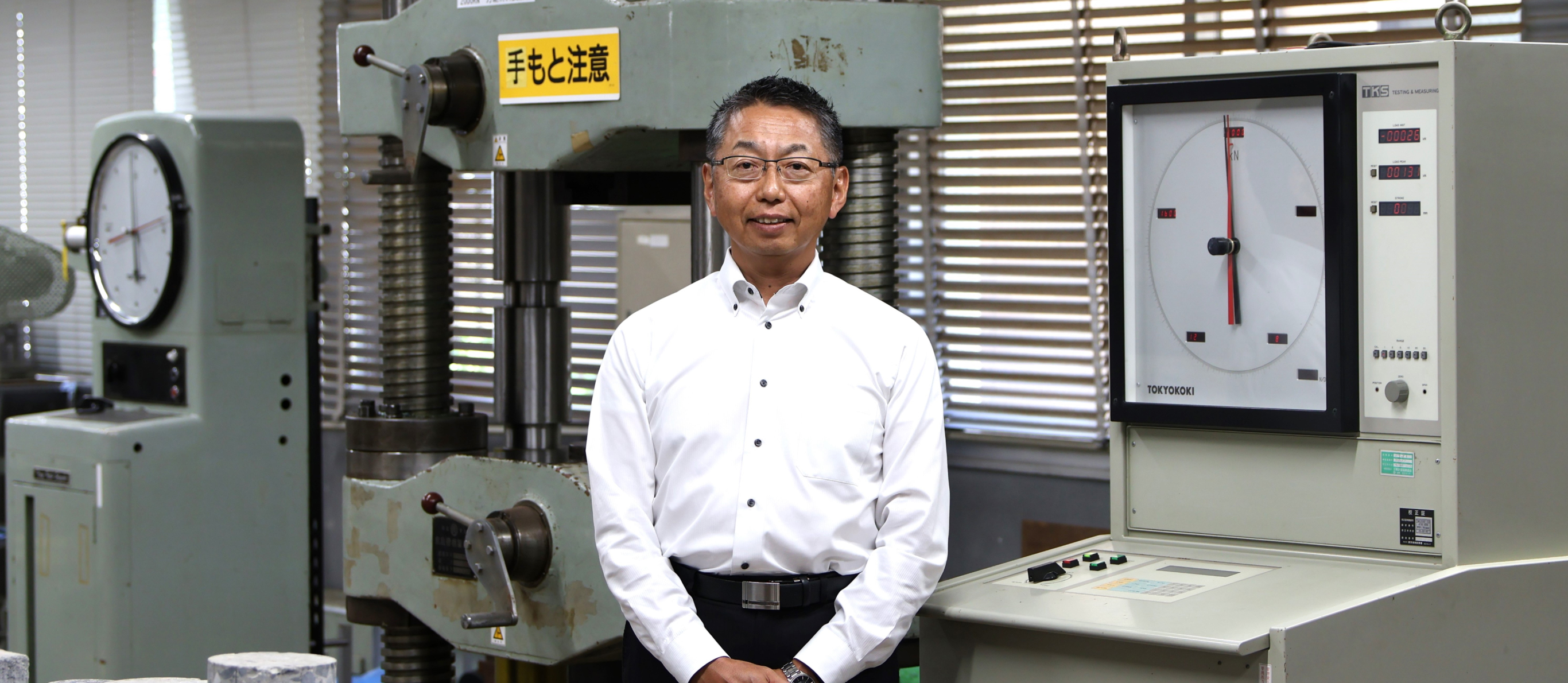
RESEARCHERS
電力技術研究所
佐藤 正俊
MASATOSHI SATOU
PROFILE
| 所属 | 電力技術研究所 |
|---|---|
| 研究・専門分野 | 土木工学、コンクリート工学、ダム工学、河川工学 |
| 学位 | 修士(工学)名古屋工業大学 博士(工学)名古屋工業大学(注)中部電力入社後に取得 |
| 趣味・好きなこと | 現場調査で鍛えた健脚を活かした山登り(低山の雪山)、DIY、農業、庭木の手入れ、自転車(折りたたみデザイン設計に一目ぼれ) 、パソコン |
| 研究キーワード | コンクリート、ダム、岩盤、グラウンドアンカー、非破壊検査手法、資源循環(産業副産物の有効利用)、ダム貯水池堆砂 |
(注)2025年8月取材時
佐藤さんの専門分野を教えてください。
大学生のときにコンクリート工学を専攻し、中部電力入社後もコンクリートに関する研究を中心に取り組んでいます。入社当初はダムの耐震関係、構造解析関係を専門とし、岩盤の評価もおこない、その後は維持管理や産業副産物のコンクリート利用などもおこなってきました。後年ではダム貯水池の堆砂や運用関係の技術などにも携わってきています。
ダムなどに使うコンクリートは、一見同じように見えますが、戦前・戦中・戦後でセメントの種類や製造方法が変遷しており、非常に奥が深いものです。そのため、それぞれの設備建設時期と劣化状態に応じた補修が必要です。最近は、写真から損傷状態をAIで評価する方法にも取り組んでいます。
コンクリートは、ダムのさまざまな分野に関係しており、ひとつの研究に取り組むと次々と新たな分野での課題が見えてくるため、それを解決していくうちに研究の幅が広がってきた感じですね。
こうした技術者になりたいと思ったのは、小学生の頃です。技術者である父が、物置小屋を自分で作っていて、その器用さに憧れましたね。土木工学を選んだのも、父の影響が大きかったかもしれません。
もうひとつは、コンピューターに興味があり、パソコンを土木分野に活かしたら面白いんじゃないかと思って、大学でコンクリートの破壊シミュレーションに取り組んだことです。この経験が設備の維持管理などに活かせるのではと感じ、結果的に中部電力に入るきっかけにもなりました。
中部電力でこの分野に携わろうと思ったきっかけは?

大学時代、大型の橋梁などの社会インフラが次々と完成し、私もそのような大きな仕事に携わりたいと思いました。
当初は電力会社について考えていませんでしたが、研究室に中部電力の方が共同研究者として来ていて、発電所建設などいろいろなプロジェクトが動いているという話をその方から聞き、面白そうだなと感じました。また、電力会社では、ダムを作るだけで終わらずメンテナンスもあり、さらに古いダムも管理するなど、さまざまな関わり方ができることを知り、魅力を感じました。
現在、どんな研究に取り組まれているのでしょうか。
コンクリートに関わる研究をメインに取り組んでいます。また、貯水池の堆砂などに関わる研究はほかの研究員のサポートという形でかかわっています。
コンクリート関連の研究では、資源循環関連や、脱炭素への貢献を目的としたセメント使用量を減らす研究に取り組んでいます。たとえば、廃棄される太陽光パネルと石炭灰をコンクリートに使用するという研究もそのひとつですね。
また、過去に取り組んで、あまり満足いく結果が得られなかった、コンクリートのひびをAIで検知するという技術などに再挑戦しているところです。
何事も、諦めずにやり続けることを大切にしています。止めたら、そこで終わりですからね。

日頃の研究の中で醍醐味に感じる部分はなんですか?
これまで知らなかったことが明らかになる瞬間ですね。意外なところで予想外の結果が見つかったり、新たな発見に出会うとうれしいです。
それから、自分が開発したものや技術が社会で役に立つことも、非常にうれしく感じますね。
今後の夢や目標について教えてください。
新しい研究にももちろん取り組んでいきたいと思っていますが、先輩方が残したものと、私の今までの経験をしっかりと整理し後輩に継承していくことが、非常に大事だなと思っています。また、コンクリート構造物の検査や補修などで培ったノウハウを地方自治体のインフラ点検などにも活かし、防災・減災に貢献したいですね。
技術面をあと少し強化・安定させれば、実現できると感じています。

技術報告(技術開発ニュース)
所属学会
土木学会
日本コンクリート工学会
電力土木技術協会
日本大ダム会議、国際大ダム会議
ダム工学会
充填技術協会
この研究者へのお問い合わせはこちら